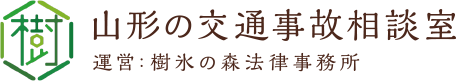後遺障害等級認定
こんなお悩みはありませんか?
- 後遺症が残ってしまったが、適正な補償を受けられるか不安である。
- 保険会社から後遺障害は認められないと言われてしまった。
- 後遺障害の申請方法や必要書類がわからない。
- 治療を打ち切られたが後遺症の症状が続いている。
- 認定結果に納得できない。
後遺障害等級とは
後遺障害等級とは、交通事故によるケガが治療を続けても完治せず、将来にわたって残ってしまった障害を14段階に分類したものです。等級は1級(最も重い)から14級(最も軽い)まであり、認定される等級によって受け取れる賠償金額が大きく変わります。
等級認定は被害者の今後の生活に大きな影響を与えるため、適正な等級を獲得することが非常に重要です。しかし、保険会社は等級を低く抑えようとする傾向があり、被害者だけで適正な等級を獲得するのは難しいケースが多いのが現状です。
認定までの流れと必要書類
後遺障害等級の認定申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。事前認定は保険会社が主導して行う方法のため、事務手続きの手間は軽減されますが、被害者にとって不利な結果になりやすいというデメリットがあります。
一方、被害者請求は被害者自身が直接、自賠責保険に申請する方法です。必要書類は主に後遺障害診断書、事故証明書、レントゲンなどの画像所見、通院歴を証明する診療報酬明細書などと多く、対応に手間がかかります。しかし、これらの書類をそろえて適切に申請することで、より適正な等級獲得を目指せるため、当事務所では対応に力を入れています。
認定されやすいポイントと注意点
後遺障害認定で重視されるのは、症状の客観性と継続性です。例えば、MRIやレントゲンなどの画像検査で異常所見があれば、客観的証拠として有利に働きます。また、事故直後から継続して同じ症状を訴え、定期的に通院していることも重要なポイントです。
注意すべき点は、治療の中断です。経済的な理由や多忙を理由に通院を辞めてしまうと、症状が改善されたと判断される恐れがあります。また、事故と因果関係のない既往症がある場合は、しっかりと区別して説明する必要があります。適切な医療機関選びも重要であり、後遺障害診断書の作成に慣れた医師に診てもらうことで認定率が上がる場合もあります。
非該当・低い等級と判断された場合の対応
後遺障害が「非該当」または期待より低い等級と判断された場合でも、諦める必要はありません。異議申立てにより再審査を求めることが可能です。この段階では、新たな医学的所見や日常生活への影響を具体的に示す証拠を追加します。
また、自賠責保険での認定に不服がある場合は、裁判所に訴訟を提起して、裁判官に判断を求めることも選択肢の一つです。裁判では、医学的な観点だけでなく、被害者の職業や生活状況なども考慮した総合的な判断がなされることがあります。
弁護士に相談するメリット
後遺障害等級認定において弁護士に相談するメリットは多岐にわたります。
まず、適切な治療や診断結果を受けるためのアドバイスが受けられます。認定に有利な医学的所見の取得方法などの専門的なアドバイスも大きな強みです。また、後遺障害申請書類の作成や意見書の添付など、専門的な知識が必要な手続きのサポートも受けられるため、認定率が向上します。
認定まで時間がかかるケースでも、その間の生活費や治療費について賠償金の内払いを交渉するなど、生活面での支援も受けられます。打ち切られた治療費についても、弁護士の介入により支払いが継続される可能性が高まるでしょう。
樹氷の森法律事務所の特徴
当事務所は、被害者請求による後遺障害等級認定申請に積極的に取り組んでいる山形の法律事務所です。代表弁護士は、損害保険会社の代理人を務めた経験や、弁護士会の交通事故相談センターにおける示談あっせん委員の経験があり、豊富な知見とノウハウを持っています。
後遺障害等級認定については、保険会社の対応に誠意が見られないケースでも、被害者請求によって適正な等級獲得を目指せます。認定には何か月もかかる場合がありますが、その間の治療費や生活費が確保できるようにサポートしながら、保険会社との交渉を進めますので、ご安心ください。
初回相談は無料で、平日夜間・土日祝日の相談にも可能な限り対応しています。相談しやすい環境づくりを心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。